診療科のご案内
外科系 麻酔科
小児麻酔研修を希望する方へ
興味を持たれた方はぜひ見学にお越しください。
フェロー採用は原則4月ですが、空きがあれば随時受け入れますのでご相談ください。
ご質問等ありましたら、下記アドレスまでメールしてください。
achmcanesthesia@gmail.com
当センター小児麻酔研修の強み
研修プログラムを終えて(山内佑允医師)
小児麻酔の世界に足を踏み入れて1年が経ちました。
複雑な上に繊細さが要求される小児麻酔をイチから丁寧に指導してくださった先生方に、まずは御礼申し上げます。これから小児麻酔の研修を考えておられる方のために、あいち小児センターでの研修の様子を紹介します。
私は、小児麻酔の経験はこれまでほとんどなかったので少し心配していたのですが、大丈夫でした。最初は、耳鼻科、眼科、外科、泌尿器科等の短時間手術を大量に経験することで、緩徐導入、挿管(声門上器具も多い)、抜管といった小児麻酔の基本の型を学びます。慣れてきたら整形外科手術等で多くの神経ブロック手技を経験します。ブロックに関しては、解剖は成人と同じなので入りやすい(むしろエコーがよく見える)のですが、サイズ感の違いに慣れることと、局所麻酔薬使用量の極量に注意が必要でした。次にいよいよ先天性心疾患の麻酔を経験します。最近症例数が右肩上がりの先天性心疾患では、心臓血管麻酔専門医を中心に作成された独自の入門レクチャーコースと心臓カテーテル麻酔(週4日)の症例を通して、心臓構造の解剖学的な位置関係および循環動態のバランスを理解します。心臓外科の手術日は週5日あるので、フェロー同士で症例が取り合いになることもなく、かなりの数の小児心臓麻酔を経験することができます。小児TEEの実務に長けたエキスパートの麻酔指導医が在籍しておられるので、私も濃厚な指導を直接受けることができました。
小児専門病院でも滅多に遭遇することができない危機的な状況(CPA、不整脈、喉頭痙攣、アナフィラキシー)への対応としては、北米式の麻酔シミュレーション教育(アネシム)が有効でした。Off the jobトレーニングとして、ケースカンファとシミュレーション実習を効果的に組み合わせて学ぶことで、急変の場で即座に対応できる突破力を身につけることができました。
さらに、研究面では、英文論文執筆や統計手法に関しての多施設合同web勉強会(ACCESS;あいち小児センター麻酔科主催)、STATAを使用した統計セミナーと生物統計解析実習(院内限定)など、極めて実践的な教育を受けることができました。臨床研究室員を兼務する指導医らの手厚いバックアップのもと、私も論文執筆に奮闘中です。
その他の面で言うと、マネジメントとリーダーシップ、医療経済、他部門とのタフネゴシエーション、英会話などなど、小児麻酔の枠組みを超えた様々なノンテクニカルスキルをも同時に学びとることができました。そして何より驚きなのが、フェローのために準備された教育セッションが、いずれも勤務時間内に行われることです。指導医・フェローお互いのワークライフバランスにとても良く配慮された職場であると感じました。
私がここで得た経験は、単なる小児麻酔研修ということに留まるものではありませんでした。あいち小児センターの研修は、困難な時代を生き抜くこれからの麻酔科医にとって必要なスキルを、小児麻酔というツールを通して総合的に学ぶことができる、最良の環境であると思います。小児麻酔を将来やるかやらないか、小児自体に興味があるかないかに関わらず、一度この環境に身を置いてみると、きっと見えてくるものがあるはずです。ぜひ一度、見学にお越しください。そして、チャンスがあれば一緒に働きましょう。
1年間で経験した麻酔症例・手技の例
- 声門上器具 166例
- 気管挿管 175例
- 新生児症例 7例
- 乳児症例 83例
- 心臓カテーテル検査
52例 - 心臓外科手術 36例
- 仙骨硬膜外麻酔 50例
- 末梢神経ブロック 39例

フェロー2年目の挑戦(大森彩加医師)
みなさんは小児病院での麻酔研修に何を求めますか?
まずは小児麻酔ができるようになる、小児麻酔の知識を増やす、等でしょうか。
私はあいち小児での1年間の小児麻酔フェローシップを終え、2年目もあいち小児でフェローとして研修することにしました。その結果、次のような目標を持つことができました。
- 長期的に臨床研究に携わり、もっと質の高い麻酔管理を追求したい。
- 海外の小児病院に留学して、さらに広い視野を持ちたい。
- 教育のストラテジーを学ぶことでチーム全体が成長する一翼を担いたい。
フェロー2年目に入ると、小児麻酔の臨床を学ぶ傍ら、自分が興味ある特定の分野にも積極的に関わっていくことが可能となってきます。小児麻酔研修を開始した当初は、今まであまり馴染んでこなかった先天性心疾患の病態生理や小児特有の気道管理など、臨床面で学ぶことがとても多く、臨床以外のことに関わる余裕はあまりありませんでした。しかしながら、1年目後半に差し掛かる頃には徐々に余裕も生まれてきました。タスクを調整できるようになったため、2つの臨床研究:「フォンタン循環に関わるCase series study」、「術中の点滴漏れ検出に関わるRCT」に携わるようになり、それらは結果として論文投稿にまで漕ぎつけました。
あいち小児では、過重労働にならないよう、労働環境には十分な配慮がなされているため、フェローであっても日中に机に向かって座学する時間が与えられます。私はこの機会にTEEについて集中的に勉強し、JBPOTを取得することができました。とくに、先天性心疾患領域に関しては、自分の目で間近に見ながらその分野を学習することで、教科書の知識と実際の症例を有機的に結びつけて考えることができるようになりました。
また、研究面で興味のあった統計・疫学についても学習することができました。多施設連携webセミナー(ACCESS)で若手向けレクチャーを担当させていただいたことも良い経験となりました。フェロー2年目以降はCase Conferenceのファシリテーションや教育レクチャーなどの教育活動にも積極的に参加させてもらっています。これらは、自分の知識の整理やファシリテーションの方法論を学ぶ良い機会になっています。
あいち小児には、小児麻酔領域で臨床留学を経験された先輩が複数おられるため、臨床留学に至るまでのプロセスや米国の小児病院での経験についてお話を伺う機会が日常的にあります。そのような話を先輩方と何気なく会話する中で、大学医局等のコネクションがなくても臨床留学が可能であることを知り、私も海外の大規模施設で麻酔や臨床研究をしてみたいと思うようになりました。そこで、次のステップとして海外臨床留学することを決意しました。フェロー2年目前半には、IELTS 等の英語能力試験やカナダ・オーストラリアの小児病院へのApplicationに取り組みました。その結果、来年度、オーストラリアのRoyal Children’s Hospital Melbourneでの臨床麻酔フェローの枠をいただくことができました。Applicationの過程では、急に入ったweb面接の日程に合わせて勤務調整が必要になることもありましたが、科長をはじめとした諸先生方がとても前向きに応援してくださったおかげで、採用面接に向けて全力で取り組むことができました。
これからフェロー2年目後半に突入します。海外留学前の1年間という貴重な期間を有効に活用するため、London School of Hygiene and Tropical Medicineの疫学修士コースに入学し、オンラインで受講する予定です。この発想に思い至ったのも、実際に科内で公衆衛生大学院をまもなく修了する指導医がいたためです。働きながら学位を取得することが可能であることを、現実味を持って認識することができたことが大きかったと思います。同じように、あいち小児で働きながら来年度公衆衛生大学院に出願する熱意のあるフェロー仲間の存在も良い刺激となりました。
以上、私のフェロー2年目としての挑戦についてご紹介しました。あいち小児では各個人の関心・興味に合わせて手厚いサポートが得られる素晴らしい環境があります。英文論文執筆、新規臨床研究プロジェクトの立ち上げ、シミュレーション教育、Quality Improvementなど、他にも挙げればキリがありません。様々なことに挑戦するフェロー仲間にも恵まれ、一緒に働いていて毎日が刺激的です。小児麻酔や臨床研究は未経験だし、苦手意識が・・・という方も心配いりません。私たちと一緒に未知の世界に飛び込みましょう!

Basic Clinical
- 国内および海外の小児病院出身の小児麻酔認定医が丁寧に指導します。
- 採用するフェローの人数を制限し、手厚い教育体制を実現しています。
(指導層とフェローの人数比を他の小児病院と比べてみてください!) - 毎月ケースカンファレンスを行っています。ここでは、小児麻酔トレーニングで経験すべき症例について麻酔指導医とフェローでディスカッションし、理解を深めます。
ケースカンファレンスの予定に関してはこちら(2024年度) - 毎月のケースカンファレンスと北米型シミュレーションを組み合わせた先進的な教育プログラムを行っています。ケースカンファレンスで知識を習得し、シミュレーションで実践に通じる能力を鍛えます。
- 毎月フェローレクチャーを行っています。フェロートレーニング期間中に習得すべき知識(臨床および臨床研究)をカバーしています。
フェローレクチャーの予定に関してはこちら(2024年度) - レクチャーやシミュレーションは、早朝や業務終了後ではなく原則として勤務時間内に行います。
シミュレーションについてはこちらのページで詳しく紹介しております。
Advanced Clinical
- 当センターは心臓血管麻酔専門医認定施設です。
- 心臓麻酔は小児経食道心エコーのエキスパートが直接指導します。
三次元コンピュータグラフィック(3DCG)を利用した経食道心エコー学習についてはこちらのページで詳しく紹介しております。 - 新生児症例含む様々な複雑心奇形の麻酔を多数経験できます。
- エコーを使った末梢神経ブロックや仙骨硬膜外ブロックが豊富です。
エコーガイド下血管穿刺についてはこちらのページで詳しく紹介しております。
フェローと指導医の相互評価システム
- 当センターでは、指導医からフェロー、フェローから指導医の相互的評価を行い、フェローへより質の高い教育が提供できるよう努めています。
評価項目について
Research
- フェローは、国内外学会発表、国際誌への論文発表に関して指導医より全面的なサポート(研究デザイン考案、研究計画書作成、統計解析、論文執筆のすべて)が受けられます。このサポートに関しては、海外臨床・研究留学経験者が英語論文の執筆までの指導を行っています。
臨床研究計画の立案、倫理審査委員会への書類提出
研究データベース作成、データ収集
データ解析、統計ソフト STATA Ⓡ 使用法
論文の構成立案、執筆(英文)
※上記以外に、麻酔科内で定期的に研究カンファレンスを行い、建設的なフィードバックを得る機会があります
- 臨床研究の立案に関しては、センター内の臨床研究室からのサポートが受けられます。
(臨床研究室主任研究員は、麻酔科医が兼任しています。) - 適宜研究カンファレンスを開催しています。研究内容や進捗状況に関して複数の指導医から建設的なフィードバックが受けられます。
- 当センターで得られた臨床データを使った臨床研究を行い、連携大学院で博士号を取得することが可能です。
- 当科では、生物統計学のレクチャーを外部参加者を含めたオンライン勉強会として提供しています。
生物統計学のレクチャーシリーズの予定に関して(2024年度)
ACCESS(Aichi Children’s Clinical Epidemiology and bioStatistics Seminar)について
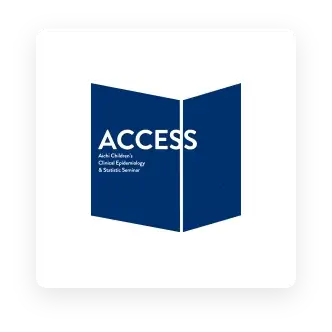
当センター麻酔科が主催する多施設ジャーナルクラブ(Web)です。
いわゆる昔ながらの抄読会ではなく、小児麻酔分野のある一つの研究を題材にして臨床疫学や生物統計の知識を整理し、その論文に対しての批判的吟味を行います。 将来的に自分で研究計画を立案できるようになることを目標としています。フェローは指導医のサポートを受けながら研修期間中に必ず1回は発表者となります。
現在のところ参加施設は東北大学、埼玉県立小児医療センター、神戸市立中央市民病院、兵庫県立こども病院です。参加希望のご施設はお気軽にご連絡ください。
小児麻酔の気道確保時における危機的合併症と関連するリスク因子に関する研究:J-PEDIAについて
Next step & Future
フェロー終了後は引き続き、当センターのスタッフとして残る道もあります。またフェロー在職中の海外小児病院への短期留学・見学を奨励しています。シンシナティ小児病院、ネイションワイド小児病院、フィラデルフィア小児病院等に人的コネクションがありますので紹介することが可能です。
1年間の小児麻酔研修を修了した2023年度フェロー3名

(左から)影山先生、越智先生、岩井先生
次年度は、3名のうち2名がスタッフとして当センターに残り、臨床研究や論文執筆を含めた発展的な小児麻酔研修を行います。1名は関西地方の大学病院に異動し、後輩たちに小児麻酔の魅力を伝えつつ、新たな分野にチャレンジします。1年間、本当によく頑張りました!
医師紹介
現在の麻酔科構成人員は、科長を含めスタッフ麻酔科医10名(+小児集中治療科兼務2名)、フェロー3名で構成されております。他にセンター内ローテートの小児科専攻医、救急科フェローや集中治療科フェロー等が加わる時があります。他院からの短期研修は現在受け入れておりません。(先天性心疾患の症例数獲得のみを目的とした研修、3ヶ月〜6ヶ月の短期研修は受け入れておりません。1年以上研修できる方はフェローとして採用します。詳しくは研修のページをご覧ください。)
